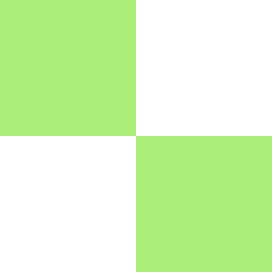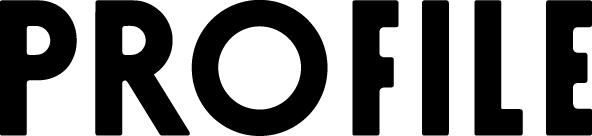ユーザベースが手がけるさまざまなサービスの背後には、これらを支えるプロフェッショナルたちの存在があります。そんな彼、彼女たちはどのような思いでユーザベースに加わり、日々の業務にあたっているのでしょうか。このシリーズではユーザベースのコーポレートITと情報セキュリティ組織で働くエンジニアたちに焦点を当て、外からは窺い知れない仕事の舞台裏をご紹介します。今回は、企業活動になくてはならない基幹業務システムの開発を司る「Biz System Management Team」のメンバー竹本賢司が、ユーザベースに入社した経緯や日々の仕事ぶり、プロジェクトの魅力について語ります。
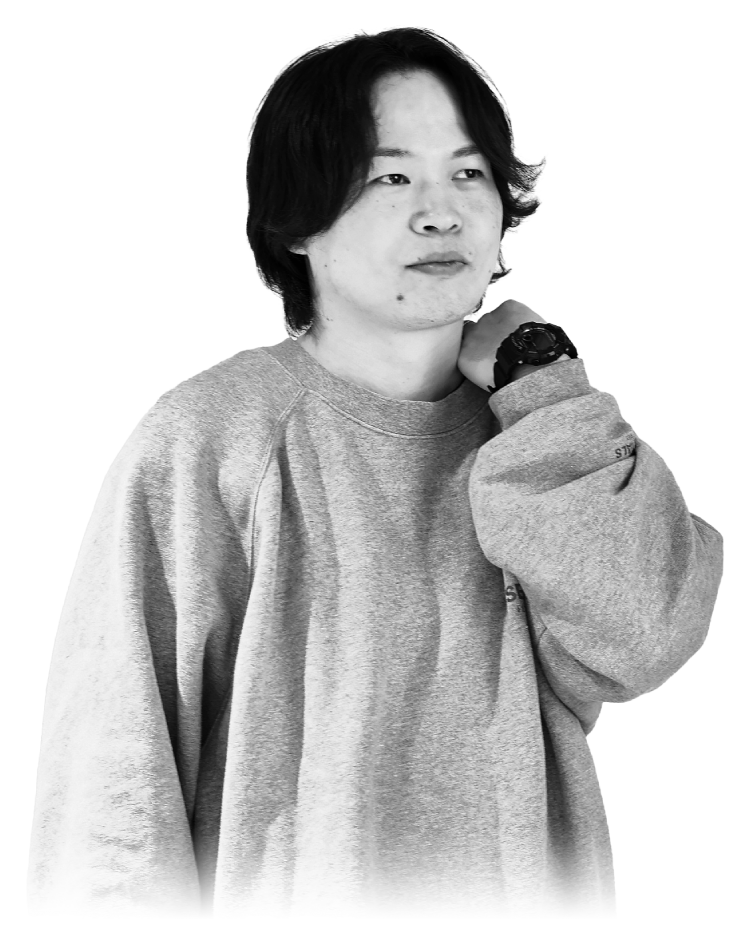
Biz System
Management Team
竹本 賢司
2012年、龍谷大学を卒業後、在阪のSIerに入社。プログラマやSEとして業務システムの構築に従事する。2017年、Salesforceの導入支援を専業とするベンチャー立ち上げに参加。中小企業のDX推進に貢献。2022年、ユーザベースに入社。組織統合を経て社内の基幹システムを司るBiz System Management Teamの一員として、スピーダ事業の業務システム開発に携わる。
# 私が貫く仕事の流儀
仕事を楽しめなければ、どうしても真っ先にできない理由を口にしてしまったり、チャレンジに臆病になってしまったりするもの。周囲から信頼してもらうためにも、腕と知恵に磨きを掛けるだけでなく、「楽しむこと」「挑戦すること」にこだわっている。


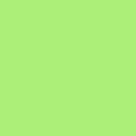
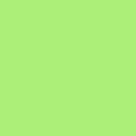

Salesforce 導入のプロがユーザベースを目指した理由
—— 現在の仕事内容を聞かせてもらえますか?
社内の情報システムを担うBiz System Management Teamで、主にSalesforceで構築されたスピーダ事業向けのCRMやSFAの開発や運用を担当しています。
—— Biz System Management Teamの担当領域を教えてください。
Biz System Management Teamは、私が担当しているセールス領域以外にも、会計、購買、人事の各領域からなる基幹業務システム全般を受け持っているチームです。
—— ありがとうございます。竹本さんのこれまでのキャリアについても聞かせてもらえますか? 前職はSIerだったそうですね。
はい。2012年に大学を卒業した後、入社した関西の独立系SIerで業務システムのコーディングや要件定義に携わるようになり、入社2年目から通常の開発業務と並行してSalesforce導入という二足のわらじを履くようになりました。2017年からは、当時の同僚たちと立ち上げたベンチャーで、地元の中小企業向けにSalesforceの導入支援をはじめたので、こちらにくるまでに2社経験しています。
—— Salesforceの導入経験が豊富なんですね。
そうですね。いまほど情報があまり手に入らなかった時代から10年以上にわたり、Salesforceの導入に関わってきましたから、経験は長いほうかも知れません。セールスフォース・ジャパンの方々と一緒にタッグを組んでお仕事をさせていただく機会もたくさんありました。
—— Salesforceの利点はどこだと思いますか?
システム構築と改修の容易さ、カスタマイズの柔軟性でしょうね。Salesforceならノーコードでシステムを構築できますし、オンプレかつスクラッチで組んだ昔ながらの業務システムなら、ベンダーに頼んでから1カ月は時間がかかるような改善でも、すぐに改修できてしまうことが少なくありません。Salesforceが零細企業から大企業まで幅広い顧客に支持されているのは、導入のしやすさと変化への強さが挙げられると思います。

—— 独立後も順調だったそうですね。なぜ転職しようと思われたのですか?
長年お客様に対し、さまざまな業務システムを提案してはきたものの、心の片隅に「現場を知らないままでいいのか」という思いが引っかかっていたんです。仕事がマンネリ化している自覚もあったので、「ここで立場を変えなくては、これ以上の成長は見込めないだろう」と思いはじめ、システムを使う立場、育てていく立場を経験しようと決めました。

—— なるほど。なぜ、たくさんの選択肢があるなかでユーザベースを選んだのでしょうか?
いくつか理由がありますが、一番大きいのは、面接で出会う人、出会う人が、ユーザベースの掲げる「The 7 Values」のどれかを体現していると実感したのが大きかったですね。ビジョンやバリューを掲げる企業は少なくありませんが、かけ声ばかりで、実態が伴っていないことがよくあると聞きます。でもユーザベースで出会った人たちは「この人は創造性を大切にしているんだな」とか「ユーザーの理想を考えるのが好きなんだな」とか、言葉の端々から、本気でビジョンを体現しようとしているのを感じさせてくれました。「こんな人たちと働けたら楽しいだろうな」と思いましたし、面接官の「やりたいことがたくさんあるので、一緒にチャレンジしていきましょう」という言葉にも背中を押されました。

—— 入社を機に、東京へ引っ越しされたのでしょうか?
いえ。実はいまも大阪に住んでいるんです。ユーザベースはフルリモート勤務がOKですし、そのための環境も整っています。関西には気心の知れた友だちがいますし、関西出身の妻はいまも地元企業で働いています。大阪から離れなくてもいいというのも入社を決めたポイントの1つでした。

組織体制の変更に伴い Salesforce 環境の刷新に取り組む
—— 冒頭に「スピーダ事業向けのCRMやSFAの開発・運用を担当している」とおっしゃっていましたね。Salesforceをどのように活用されているんですか?
スピーダなどの法人向けのサービスを提案するセールス担当者やCS担当者を支援するためにSalesforceを利用しています。ほかの会社とくらべて使い方に大差ありませんが、アーキテクチャについては、いくつかの点でちょっと特別かも知れません。
—— と、いいますと?
一般的にSalesforceは1社1環境が普通なのですが、私が入社した当時、社内で利用しているSalesforce環境は4つもあったんです。
—— なぜ、4つもあったのでしょう?
セールス担当が取り扱うプロダクトごとにSalesforceを分けていたからです。レベニュー体制がプロダクトカットだったときは、そのほうが効率的だったのですが、2024年度からレベニュー体制が顧客ニーズで分けられるようになり事情が変わりました。営業管理システムを変えずに組織変更した場合、顧客の情報を把握しようと思うと、プロダクトごとに分かれたSalesforce環境にログインしなければなりません。これでは営業効率はガタ落ちです。元々環境が分かれていることによって、事業全体での分析がスムーズにできない課題もあったので、2022年から1年がかりでSalesforce環境のデータ統合に取り組みました。
—— すぐに1つのSalesforce環境に集約できたのですか?
いえ。環境ごとにかなり複雑なカスタマイズを加えていたこともあって、性急に1つの環境に統合するのは、営業担当者の利便性を著しく下げる結果になりかねません。そのため、まずは環境統合ではなくデータ統合する道を選びました。具体的には4つのSalesforce環境の上に、もう1つSalesforce環境を設けてデータを集約し、ここにログインすれば、ユーザベース全体ですべての顧客情報を集められるアーキテクチャに変更することにしたんです。
—— サービスごとのこだわりや営業スタイルを守りつつ、クロスセルしやすい環境を整えたわけですね。
そうですね。タイミングのいいことに、お付き合いのあるセールスフォース・ジャパンの営業担当からデータ連携に使える「MuleSoft Composer を試用してみませんか」と、お声がけいただき、予定通りプロジェクトを終えることができました。当時、MuleSoft Composer は日本未発売のプロダクトだったこともあり、本社のエンジニアのみなさんともやり取りさせていただいたり、プロジェクト終了後にSalesforce World Tour Tokyo 2023に登壇させていただいたりと、個人的にも思い出深いプロジェクトになりました。
—— いまはどんなプロジェクトを?
現在は、2024年度のレビュー体制変更による課題解決を目指し、2023年11月からSalesforce環境の環境統合に取り組んでいます。さきほどお話したように、1つのSalesforce環境に入ればすべての契約状況が確認できるようになったとはいえ、1人のセールス担当者が複数プロダクトを販売するとなると、商談内容をそれぞれのSalesforce環境に入って入力しなければならない状況は変わりません。それではあまりにも効率が悪いので、2023年11月からSalesforce環境の統合に取り組みはじめました。2024年内に4つある環境のうち2つを統合できたので、2025年度には残りの2つも統合し、1度のログインで営業管理を完結できるようにする計画です。
—— 難しそうな取り組みです。
そうですね。いくら開発しやすいSalesforceといえども、ステークホルダーの意見を取りまとめ、レベニュー組織に必要な機能を網羅するのは容易ではありません。ただ、これが自社開発されたシステムだったり、カスタマイズの余地が少ないSaaSだったら、1年ではおそらく開発の目処すら立たなかったと思います。
—— 前職での経験が活きることもあるのでは?
そうですね。Salesforceに限ったことではありませんが、業務システム系SaaSには使ってみなければわからない独自の仕様や制限があるものです。それを知らずに設計してしまうと、自社開発では目にすることがないエラーが返ってきてしまい、手詰まり状態になってしまうことがあります。こうした状況を招かないようにするのが、私たちBiz System Management Teamの腕の見せどころ。前職でさまざまな状況を経験したからこそ、防げるトラブルがあるのは確かです。


急激な変化に柔軟に対処できるよう、腕と知恵を磨き続ける
—— 入社して3年。率直な感想は?
「想像以上にすごい人だな」とか「ここまでやるのか」とか、ポジティブなギャップはあっても、入って後悔するようなネガティブなギャップはありませんね。経営陣や現場の期待に応えるのは大変ですが、すべての部署がチャレンジングな取り組みに対して前向きですし、その時々で最善の方法を主体的に選択させてくれるので、業務システムを預かる身として、とても仕事がしやすいですね。

—— 仕事にやりがいを感じているのがよくわかりました。これから、組織として、個人として、会社にどのような貢献をしたいですか?
ユーザベースは、とても変化に富んだ企業です。伸び盛りのサービスを数多く抱えていますし、組織体制も頻繁に変わります。そのため、業務システムにも、アジャイルかつスケールを前提とした取り組みが求められるのはいうまでもありません。その時々で必要とされる価値をいち早くお届けできるよう、Salesforceに限らずあらゆる選択肢を採れるだけの腕と知恵を磨いておかねばと思っています。

—— 次のプロジェクトはもう見えているのでしょうか?
近々、「プロダクトの利用ログをSalesforce上で見える化し、CS活動をスムーズにする」、また「複数の新プランを売りやすくする」プロジェクトがはじまる見込みです。こうしたプロジェクトが立ち上げられるのも、先に挙げたSalesforce環境の統合という土台があってのこと。ですから、今後はいままで以上に使いやすいシステムづくりに注力できると期待しています。
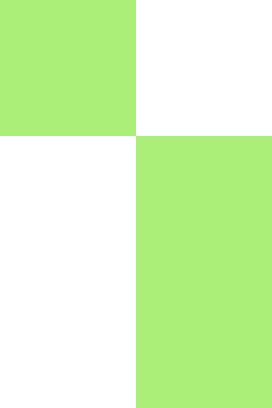
チャレンジ志向があり、成し遂げたい目標がある人へ
—— いま、Biz System Management Teamにはどれくらいの方が在籍していますか?
Biz System Management Teamの正社員メンバーは全体で6名ほどです。生成AIの活用など、やりたいことは山のようにあるので、少しでも多くの方に興味を持ってほしいですね。
—— なるほど。では今後チームに加わってほしいと思うのはどんな方ですか?
システム開発や導入、運営のエンジニアリング経験に加え、たとえば「レベニューサイドにしっかり貢献できるスキームをつくりたい」など、具体的な目標がある人とご一緒したいですね。Salesforceに限らず、CRMやSFAに関する興味や知見を持っていらっしゃる方であれば、なお嬉しいといったところです。
—— 竹本さんが、普段仕事で意識していることについても教えてください。
意識しているのは「仕事を楽しんでいるか」と「挑戦しているか」の2つです。仕事を楽しめていないと、何か依頼を受けたとき、真っ先にできない理由を口にしてしまいがちですし、そういう状態に慣れきってしまうと、チャレンジにも臆病になってしまいます。周囲のみなさんに「あの人たちに相談したら大丈夫」と信頼してもらえるよう、常に「楽しんでいるか」「挑戦しているか」と、自分に問いかけています。
—— ありがとうございます。では、最後にユーザベースに興味をお持ちの読者のみなさんにメッセージをお願いできますか?
はい。ユーザベースは、IT投資に対する解像度がとても高いので「社内政治をしないと物事が進まない」「技術的なチャレンジができない」といったフラストレーションとは無縁です。リモートワーク環境も整っており、仲間同士助け合う文化も根付いています。興味のある方はぜひカジュアル面談でお話させてください。多くのみなさんの応募をお待ちしています!